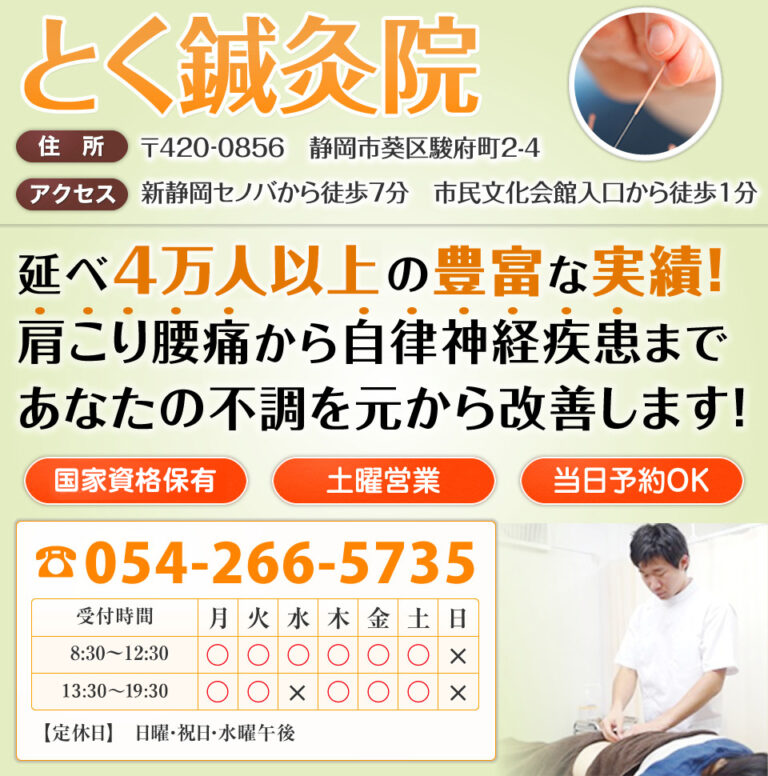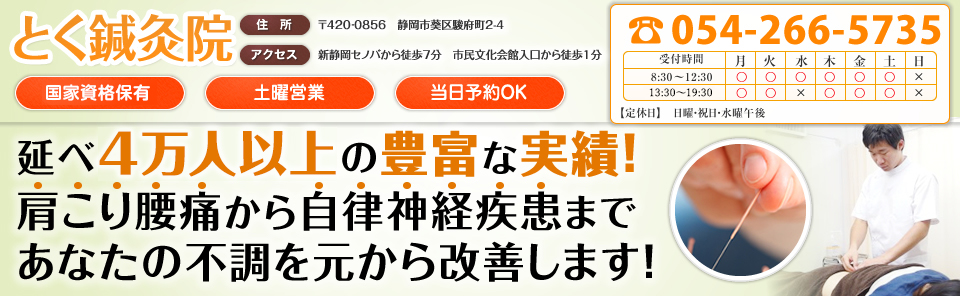更年期障害について
更年期(45歳~55歳)に生ずる不定愁訴を更年期症状といい、その症状が日常生活に支障をきたすものを更年期障害といいます。
日本産婦人科学会の定義では更年期は「生殖期から生殖不能器への時期で、加齢に伴い性腺きのうが衰退し、特に卵巣では排卵などの機能が消失しはじめ、やがて月経不順から完全に閉止する閉経期に至り、そのごは性腺分泌機能が低下・安定する。わが国では45~55歳くらいが更年期の時期に相当する」とされています。
発症のメカニズムは不明ですが、現在のところでは、次の3つの要因が指摘されています。
- 内分泌因子:卵巣機能の低下・エストロゲン(女性ホルモン)の欠乏
- 社会・文化的因子:母親的役割終了・職場での人間関係
- 心理・性格因子:性格・家族関係の問題・老化の意識・健康問題
診断の決め手は①更年期であること、②卵巣機能が低下していること(閉経か月経異常)、③更年期症状があることです。
更年期症状は次のようなものが挙げられます。

現代医学的治療
現在の日本においては、更年期障害に対して次のような治療がなされています。
- ホルモン補充療法
- 精神安定剤
- 抗うつ剤
- 自律神経調整剤
- 漢方薬
- 鍼灸治療
- その他:心理療法、カウンセリング、スポーツ療法、文化活動など
更年期障害に対する鍼灸治療
更年期障害は東洋医学的アプローチによって治療していきます。
東洋医学では更年期障害のこと絶経前後諸症といいます。
黄帝内経素問 上古天真論には
「七七にして任脈の脈虚し、大衝の脈衰少し、天癸竭き、地道通ぜず、ゆえに形壊えてこなきなり」とあります。
解説すると七七つまり49歳で腎気が不足することで、天癸の欠乏が起こり、衝脈・任脈の機能が低下して、閉経になるということです。
そして腎気が不足することで、肝・心・脾の気血か欠乏することで症状が発症するといわれています。
具体的な当うよう医学的な原因としては
- 腎陰虚
- 腎陽虚
- 肝腎陰虚
- 肝陽上亢
- 心腎不交
- 脾腎陽虚
などが挙げられます。
腎陰虚
腎陰の虚損によっておこります。
のぼせ、急な発汗、手足のほてり、口や舌の渇きが主症状となります。
経穴
腎兪(じんゆ)
太谿(たいけい)
復溜(ふくりゅう)
三陰交(さんいんこう)
などのツボを中心に施術をしていきます。
腎陽虚
腎陽の虚損によって起こります。
寒がり、四肢の冷え、頭のふらつき、耳鳴り、足腰がだるくなるが主症状となります。
経穴
腎兪(じんゆ)
太谿(たいけい)
関元(かんげん)
などのツボを中心に施術していきます。
肝腎陰虚
腎陰虚が発展すると肝陰の不足が起こります。
のぼせ、急激な発汗、手足のほてり、口や舌の渇き、めまい、不眠などが主な症状となります。
経穴
復溜(ふくりゅう)
照海(しょうかい)
肝兪(かんゆ)
腎兪(じんゆ)
太谿(たいけい)
などを中心に施術していきます。
肝陽上亢
腎陰虚が発展し肝陽が抑えられなくなることで、肝陽が上に上がってしまう。
のぼせ、急激な発汗、手足の火照り、口や舌の渇き、頭痛、顔面紅潮、精神的興奮、怒りっぽいなどが主症状となります。
経穴
太衝(たいしょう)
合谷(ごうこく)
風池(ふうち)
肝兪(かんゆ)
腎兪(じんゆ)
太谿(たいけい)
復溜(ふくりゅう)
といったツボを中心に施術していきます。
心腎不交
腎陰が不足して心陰が滋養できないと、心陰は心陽を抑制できなくなるため、心陽が亢進します。
のぼせ、急な発汗、手足のほてり、口や舌の渇き、不眠、心悸などがおもな症状となります。夢を見やすかったり、忘れっぽくなったりします。
経穴
腎兪(じんゆ)
心兪(しんゆ)
心門(しんもん)
などを中心に施術していきます。
脾腎陽虚
腎陽は脾陽を温め、脾の運化作用を補助しているため、腎陽虚が進むと脾腎陽虚に移行します。
寒がり、四肢の冷え、頭のふらつき、精神不振、痩せ、下痢、足のむくみなどが主な症状となります。
経穴
足三里(あしさんり)
脾兪(ひゆ)
中脘(ちゅうかん)
太谿(たいけい)
などを中心に施術していきます。
多くの不定愁訴があっても、東洋医学的なアプローチによって全身を調節することで、自然治癒力が上がりますので一度にすべての症状が軽減することも多くみられます。